第8回「半田沼の主」
第8回「半田沼の主」
昔、むかし、半田山の方さは、押(おし)の関、押え(おさえ)の関つうのあって、山の中腹あだりさは、東(あずま)街道(かいどう)つうの通ってだんだどい。
もとの半田山、古沼の方だない。その東街道は人だの牛だの通る大事な道路だったんだない。
あの有名な金売吉次は、平泉と京都の間を往き来して、金銀財宝運んで暮してだんだない。
半田山さかがったとき、荷物積んだ牛が暴れだして、やがてのごとに、沼の一番深い所さ、荷物も牛も沈んじまったんだどい。
同行の人らも手伝ってくっちゃげんとも、深い沼の中からは、何も浮いてこながったど。「たしか、牛の背中さ積んだ金銀財宝、重石の役目になって浮がばねんだべ。」なんていう噂がうんとひろがったんだどい。
金売吉次の牛が赤(あが)牛(べご)だったがら、このあだりの人は、ぐうっと後になってから、「半田沼の主は赤牛なそうだ。ずんない赤牛入っているそうだ。」って語られるようになったんだど。まあ話の種よない。こんじぇ、おしまいだぞい。
金売吉次(かねうりきちじ)とは平安時代末期の商人で、奥州で産出される金を京で商う事を生業としたとされる人物である。源義経が奥州藤原氏を頼って奥州平泉に下るのを手助けしたとされる。実際に「吉次」なる人物が実在したかどうかは不明。
平安時代の詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
商人の詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
奥州の詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
金の詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
京の詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
源義経の詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
奥州藤原氏の詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
奥州の詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
平泉の詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
我々取材班は、話の種をもとに現地に向かいました。詳しくは町ホームページへ
我々ちょろんけ隊は、残雪残る初春の半田沼に向いました。
今回の目的地は現在の半田沼ではなく、通称「古沼」と地元で言われる旧半田沼を目指しました。
古沼は現在の半田沼の西側に位置し、100年前の半田山の地滑りによって移動しました。その痕跡を見つければと思い出発。


古沼に一番近い半田沼北口駐車場の近くの半田山登山道から出発。3月初旬で雪解けが始まったばかり。


100メートルほど登ると古沼にたどり着きます。斜面に杉林と雑木林があり、すり鉢状になっており、水が溜まれば沼のようにみえる?すぐ近くには昨年、半田山復興100周年記念植樹が行われた林があります。


杉林の中を下ると木が茂っていない窪地にでました。古沼の底の部分だと思われます。沼というより、水深1メートルにも満たない池のようでした。


左の写真が3月に撮影したもので右が4月に撮影したもの。雪が溶けているだけでなく、水位もだいぶ下がっていました。聞いた話では夏になるとほとんど干上がり、水たまり程度になるそうです。まさに古沼は伝説にふさわしい幻の沼かも?


古沼にそそぐ沢をみつけたので上流辿りました。すると山の中に一直線に雪が溶けている部分ありました。獣道のようですが、獣の足跡がありません。さらに進みました。


進むこと200メートル。四方を鉄条網で囲まれ、シートで包まれた構造物にたどり着きました。どうやら簡易水道の水源のようです。早速、北半田の山に詳しい方に電話して伺うと、銀山地区の皆さんが飲んでいる簡易水道の水源地だとわかりました。雪が一直線に溶けていたのは浅く埋められている水道管の熱で雪が溶けたようです。

水源地周辺に黒い水道管に使われたと思われるパイプが落ちていました。
取材を終えて…
今回幸いにも氷に覆われた古沼を見ることができました。100年前の半田山崩落で忘れられたと思っていましたが、古沼の水は現在でも地元も皆さんに大切に使われており、半田山の主の伝説と同様、忘れ去られてはいない事がわかりました。
次回の取材は「世試し」。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育文化課 生涯学習係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2403
ファクス:024-582-2470
メールフォームによる問い合わせ
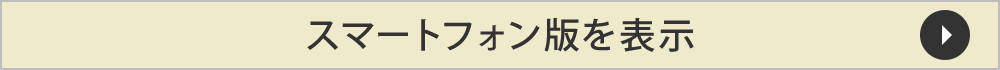


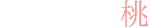
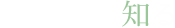
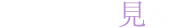
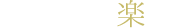
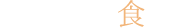
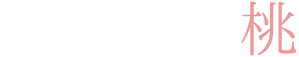
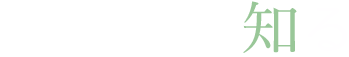
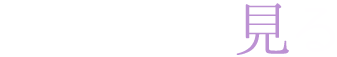

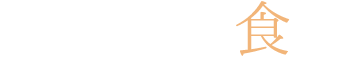
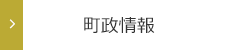
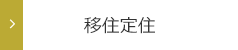
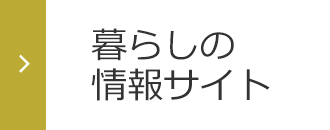
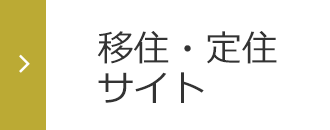



更新日:2018年03月16日