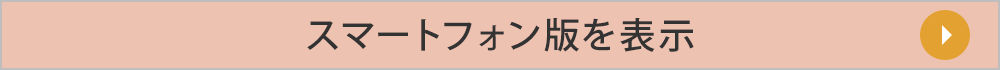認定こども園について
更新日:2024年06月03日
施設の概要


認定こども園 令和7年4月開園予定
|
項 目 |
現 在 |
今 後(令和7年4月1日~) |
|
名 称 |
醸芳保育所 |
(仮称)こおり醸芳こども園 |
|
開園年月日 |
昭和26年4月1日 |
令和7年4月1日(予定) |
|
定 員 |
120名 |
195名 (0~2歳120名 3~5歳75名) |
|
敷地面積 |
2,585.94平方メートル |
約5,445.38平方メートル |
|
建物面積 |
802.6平方メートル |
約1,821.12平方メートル |
|
建築年月日 |
昭和56年1月 |
令和7年2月(予定) |
|
構 造 |
鉄筋コンクリート造平屋建て |
木造平屋建て |
幼児保育・教育のあり方に関する町の方針
◆「醸芳保育所」の機能は、令和7年4月の「幼保連携型認定こども園」開園時に完全移行
○ 「醸芳幼稚園」は存続
○ 町が独自に実施している子育て支援策の継続
・保育料軽減、幼稚園給食費の無償化や制服支給など
◆ 町と認定こども園との連携・協力
○ 「待機児童ゼロ」の堅持
○ 幼児保育・教育における質の向上
○ 小学校への円滑な接続
今後とも「心身ともに健全な桑折っ子の育成」に努めてまいります。
認定こども園とは?

認定こども園に係る説明会について
5/11に社会福祉法人松葉福祉会主催による保護者説明会を実施しました。
認定こども園開園に係る保護者説明会資料 (PDFファイル: 10.4MB)
認定こども園に係る運営内容等について(お知らせ)
現在の醸芳保育所の機能については、令和7年4月に開園予定の民設民営による幼保連携型認定こども園に完全移行することとなりますが、移行後においても、町で独自に実施している子育て支援策を継承するとともに、多様化する保育ニーズに応えながら、「待機児童ゼロ」の堅持はもとより、幼児保育・教育における質の向上と小学校への円滑な接続に取り組むよう、社会福祉法人松葉福祉会との間で協議を重ねてまいりました。
具体的な認定こども園に係る運営内容等については、5月11日に開催された事業者の説明会において、保護者の皆様からご質問がありました部分も含めて、次のとおり項目ごとにまとめましたのでお知らせします。
|
項 目 |
回 答 |
|
|
1 |
待機児童ゼロの堅持について、どうなるのか。 |
待機児童ゼロの堅持は、継続していきます。 |
|
2 |
保育料及び延長保育料はどのようになるのか。 |
保育料については、0~2歳(3号認定)は、現行保育料に変わりはありません。また、3~5歳(2号認定)の保育料は、現在、「幼児教育・保育の無償化」に伴い、無料となっていることから保護者負担は生じません。 また、延長保育料(18:00~19:00)については、本来であれば保護者負担が生じることとなりますが、事業者に対して町で助成することにより、今までと同様に保護者負担は生じないようにします。 |
|
3 |
預かり保育料はどのようになるのか。 |
保育を必要としない3~5歳(1号認定)の預かり保育料については、醸芳幼稚園と同様に平日500円、土曜・長期休業中(夏季休業や冬季休業など)700円までは保護者負担とし、それを超えた利用料金は、事業者に対して町で助成することにより、保護者負担については、現在と変更ありません。 また、教育時間終了後も保育が必要と認定を受けた場合(新2号認定)は、「幼児教育・補償の無償化」に伴い、日額450円までは無償となりますが、それを超えた利用料金は、事業者に対して町で助成することにより、保護者負担については、現在と変更ありません。なお、月26回以上利用した場合は、醸芳幼稚園と同様に保護者負担が生じます。 |
|
4 |
認定こども園に在籍していない子どもの一時預かりについて、日数制限はあるのか。 |
在籍していない子どもについても、0歳5カ月から、一時預かりの利用は可能ですが、保育が必要な理由や事情を確認しながら対応します。日数制限についてはありませんが、予約制で1回の予約で2日まで予約が可能です。ただし、施設の都合により利用できない日があります。 |
|
5 |
給食費は、無償となるのか。 |
醸芳幼稚園と同様に平日の給食については、事業者に対して町で助成することにより、無償とします。一方で、土曜日・長期休業中の給食については、保護者負担となります。(醸芳幼稚園については、土曜日・長期休業中は給食の提供がなく、弁当持参のため)なお、給食調理は業者委託し、自園において調理します。 |
|
6 |
醸芳幼稚園は、認定こども園と同様に、毎日給食となるのか。 |
醸芳幼稚園においても、認定こども園と同様に、平日については完全給食を実施します。 |
|
7 |
制服は、無償なのか。 |
町独自の子育て支援策として、醸芳幼稚園の入園祝品に制服を支給しています。認定こども園については、醸芳幼稚園の制服相当金額分を事業者に対して町で助成することで、保護者負担の軽減を図りますが、一部保護者負担が生じます。 |
|
項 目 |
回 答 |
|
|
1 |
3歳になった際に、認定こども園から醸芳幼稚園に行く子どもが慣れ親しんだ施設や先生から離れることについて、どう考えているのか。 |
現在でも醸芳保育所から醸芳幼稚園に入園する時に、施設やクラス、先生が変わるなど、同様の状況となっていますが、子どもは、適応能力が高く、環境の変化も学びの一つとして前向きに捉えています。また、醸芳保育所等で勤務している会計年度任用職員で、認定こども園での雇用希望がある場合には、前向きに検討をいただいております。 |
|
2 |
幼児保育・教育のあり方はどうなるのか。 |
醸芳幼稚園と認定こども園が、それぞれの特色を活かしながら、交流する機会を設けるなど連携し、お互いに切磋琢磨し、サービス充実を図っていくとともに、醸芳幼稚園においても、今まで以上に魅力ある幼児保育・教育の充実に努めてまいります。 |
|
項 目 |
回 答 |
|
|
1 |
保育時間はどのようになるのか。 |
認定こども園における保育時間については、午前7時から午後7時までとなります。 |
|
2 |
仕事が休みの場合でも、預けて構わないのか。 |
用事等があり、子どもを預けたい場合は、預けていただいても構いません。 |
|
3 |
醸芳保育所は、育児休業取得の場合は退所となるが、認定こども園ではそのまま入園できるのか。 |
育児休業取得中の場合でも、保育が必要な時間は預けることが可能です。なお、保育短時間の区分を設けていないため、保育料の変更はありません。 |
|
4 |
在勤者の子どもは、入園できるのか。 |
町内在住者を優先し、年度内の受け入れ状況を見極めながら、体制に余裕が生じる場合に町外在住者(在勤者)の子どもについては受け入れ可能です。 |
|
5 |
醸芳保育所から認定こども園に移行する際に、慣らし保育は行うのか。 |
醸芳保育所からの継続児については、原則、慣らし保育は考えていません。ただし、個人差があるので慣らし保育が必要な場合は、保護者の方との相談になります。なお、令和7年4月から初めて認定こども園に入園する場合は通常どおり、慣らし保育を実施します。 |
| 6 |
子どもの受け渡しはどこで行うのか。また、混雑した場合、受け渡しに時間がかかるのではないか。 |
3歳未満児については、各保育室での受け渡しとなります。3歳以上児については、遊戯室兼ランチルーム前の場所に職員を配置し、受け渡しを予定しています。なお、醸芳保育所より30分早い、午前7時に開園するため、登園時間は分散されます。 |
| 7 | 朝早く預ける場合には、合同保育の対応となるのか。 | 発達に応じてクラス分けはしますが、職員配置の関係上、合同保育となります。 |
| 8 | 病児・病後児保育(自園型)事業の内容はどのようなものか。 | 認定こども園に通園している園児が対象であり、園で預かっている間に、体調不良になった場合、保護者が迎えに来るまで、専任の看護師が保健室で子どもを預かる事業です。 |
| 9 | 医療的ケア児について、今まで受け入れたことはあるのか。また今後はどうなのか。 | 今まで受け入れた経過はありません。なお、専任の看護師を1名配置しなければならないため、運営体制を整えることが難しいことから、今後も受け入れる予定はありません。 |
| 10 |
子どもの発達状況によって、クラスの対応をしていただけるのか。 |
発達状況に応じて、下のクラスで保育するなどの対応をしてまいります。 |
| 11 | 3歳以上児は連絡帳を使用するのか。 | 3歳未満児は連絡帳を使用し詳細に記載しますが、3歳以上児は必要に応じて使用します。また、毎日の活動報告については、各クラスの活動内容を玄関に掲載します。 |
| 12 |
醸芳幼稚園と同様に預かり保育時は、別の部屋で活動するのか。 |
教育時間終了後も、午睡やその後の活動は同じ部屋で実施します。 |
| 13 | 町では、ホームページで保育所や幼稚園での活動写真を掲載しているが、認定こども園でも同様に掲載するのか。 | ホームページに掲載する予定はありません。行事の際はカメラマンを呼び、撮影した写真を保護者に購入していただきます。また、園のお便り等で活動の様子をお知らせします。なお、子供のプライバシー保護については十分注意してまいります。 |
| 14 | 登園・降園を確認するためのシステム導入は予定しているのか。 | 松葉福祉会で運営している他園同様にシステムの導入を予定しています。 |
|
項 目 |
回 答 |
|
|
1 |
入園決定は誰が行うのか。また、定員以上の入園希望があった場合どうするのか。 |
1.共働き世帯などの保育が必要な子ども(3~5歳:2号認定)は、町で入園決定します。定員超過の場合は、原則、0~2歳児の兄弟姉妹の入園を優先し、町で決定します。 2.保育を必要としない子ども(3~5歳児:1号認定)は、認定こども園で入園決定します。定員超過の場合は、認定こども園において厳選な調整を行います。 |
| 2 | 3歳未満児で認定こども園に入園後、3歳以上児になった際に醸芳幼稚園へ入園する場合もあるのか。 | その場合もあります。選択肢があるので、どちらに行くか検討の上、お決めください。 |
|
項 目 |
回 答 |
|
|
1 |
スーパーマーケットやアパートが隣接しており、人通りが多いが、子供のプライバシーやセキュリティ面をどう考えているのか。 |
駐車場と施設の間に、フェンスや植栽を行うことにより、自然に溶け込むような作りをすることでプライバシー保護に十分注意するとともに、各クラスや駐車場に防犯カメラを設置するなど、独自のセキュリティシステムを用いることで防犯対策を講じます。 |
|
2 |
隣接しているアパートから3~5歳児の保育室が見えると思うが、何か対策するのか。 |
園舎北側に格子窓を設置するなど、アパートから保育室が見えないような対策を、検討していきます。 |
|
3 |
プールの設置は、考えているのか。 |
プールの設置は、中庭のウッドデッキに組み立て式のプールを設置し、使用しない時は、撤去する予定です。 |
|
4 |
園庭内にトイレの設置をするのか。 |
トイレを園舎東側2歳児の保育室隣に配置し、園舎内と園庭どちらからでも利用できるようにする予定です。 |
|
5 |
職員及び保護者の駐車場はどこか。 |
園舎北側駐車場は、36台程度整備を予定しており、基本的に保護者駐車場となりますが、一部職員用としても利用します。また、園舎南側駐車場は、職員用として確保しておりますが、空いている場合はご利用いただいても構いません。 |
|
6 |
駐車場内にも歩行者用の歩道を検討してもらいたい。 |
醸芳幼稚園と同様に、駐車場内に歩道を設置する予定はありませんので、保護者の皆様には周りに注意しながら登園をお願いします。 |
|
7 |
駐車場の幅を広くしてもらえないか。 |
駐車場の幅については、2.5メートルを予定しております。 |
|
8 |
園舎南側のフェンスは、メッシュフェンスだと思われるが、近年自動車のアクセル等の踏み違いによる事故が多発していることから、事故防止対策の検討はしているのか。 |
園舎は、駐車場よりも40~50センチ高い位置にあります。また、保育室を駐車場から距離を開けるとともに、フェンスも設けており、フェンス近くには緑化推進のため植栽も進める予定です。なお、園舎南側駐車場は、基本的に職員駐車場であるため、一般客が利用することはないと思われます。 |
|
項 目 |
回 答 |
|
|
1 |
他市では、私立保育園に補助金を出しているが、町では運営補助金を考えているのか。 |
隣接市同様、運営補助金について検討していきます。 |
|
2 |
遠くに住んでいる家庭のために、送迎バスを町で用意できないか。 |
現行どおり、送迎バスの運行については、考えていません。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育文化課 こども教育係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2403
ファクス:024-582-2470
メールフォームによるお問い合せ