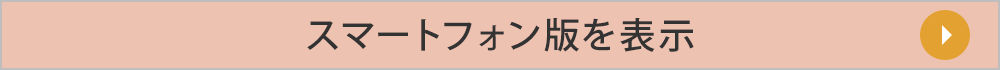固定資産税について
更新日:2025年04月28日
固定資産税は、毎年基準日(1月1日)時点で、町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、税金を負担していただくものです。
固定資産税の基準日
固定資産税の基準日は、毎年1月1日です。
納税義務者
基準日(1月1日)時点の固定資産の所有者です。
所有者とは、登記簿謄本に登録されている人をいい、未登記の土地・家屋と償却資産については、1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
ただし、所有者として登記簿謄本に登録されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
固定資産の価格と評価
固定資産の価格は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価し、町長が価格を決定します。決定された価格は、固定資産課税台帳に登録されます。
なお、土地・家屋の価格については、3年ごとに見直すこととされています。
土地の評価
土地の評価は、「固定資産評価基準」によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定めれた評価方法により評価します。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
宅地
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。
農地、山林
状況の類似する地区ごとに標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して評価します。ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から、造成費相当を控除した価格によって評価します。
牧場、原野、雑種地等
売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。
家屋の評価
家屋の評価は、「固定資産評価基準」によって、再建築価格(評価対象となった家屋と同一のものを評価の時点において同一の場所に新築するとした場合に必要とされる建築費)を基準とする方法によって評価します。ただし、在来分の家屋については基準年度(3年ごと)に評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、据え置かれます。
評価替え
前述のとおり、土地・家屋については、原則として3年に一度、価格の見直しを行います。これを「評価替え」といいます。それ以外の年度については、価格を据え置くこととなります。
ただし、第2年度または第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋、土地の地目変更、家屋の増改築などがあった場合は、評価替えの年度に関わらず、新たに価格を決定することになります。
なお、償却資産については毎年度1月1日の資産の保有状況を申告していただき、経過年数に応じて減価償却を行うため、評価替えの制度はありません。
評価替え年度以外の価格の下方修正(土地)
土地については、地価の下落が著しい場合など、価格を据え置くことが適当でない場合は、評価替え以外の年度についても、下方修正する場合があります。
課税標準額と税額
固定資産税は、
税額=課税標準額×税率(1.4%)で算定されます。
課税標準額
土地:評価額をもとにするほか、税の負担を調整する制度を適用して計算します。
家屋:基本的には、評価額=課税標準額となります。
償却資産:資産の取得価格に、経過年数に応じた原価償却率を乗じて計算します。
住宅用地の特例
住宅用地(住宅が建築された土地)は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、特例措置が適用されます。
●小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額は価格の6分の1の額となります。
●一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額は価格の3分の1の額となります。
例えば・・・・・
300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
!!注意!!
住宅用地とは、基準日(1月1日)現在、住宅の敷地に利用されている土地をいい、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地となります。
したがって、基準日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはなりません。
ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うことがあります。
税額の負担調整措置
固定資産税は、評価額をもとに課税標準額、税額を算出します。地価が上昇している場合は評価額も同じように上昇します。
しかし、評価額に合わせて課税標準額を上昇させると、税額も上昇し納税者の負担が急激に増えることになります。そこで、課税標準額を少しづつ引き上げ、税額を段階的に上げていく負担調整措置がとられています。この負担調整措置により、評価額が上がっていなくても税額が上がることがあります。
例:税負担が段階的に上昇する場合
【住宅用地】
今年度の本来の課税標準額に達するまで、本来の課税標準額の5%分ずつ税負担が上昇します。
●課税標準額=前年度の課税標準額+本来の課税標準額の5%
【一般農地】
負担水準(前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度達しているかを示すもの)に応じ、年々なだらかに課税標準額が上昇します。
●課税標準額=前年度の課税標準額×負担調整率
| 負担水準 | 負担調整率 |
|---|---|
| 0.9~ | 1.025 |
| 0.8~0.9 | 1.05 |
| 0.7~0.8 | 1.075 |
| ~0.7 | 1.10 |
新築住宅への減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
適用要件
1.専用住宅や併用住宅であること。
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
2.床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
※一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上になります。
減額される範囲
減額対象となるのは新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみとなります。そのため、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その部分が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1の額が、減額されます。
減額される期間
一般住宅・・・・・・・・・・新築後3年度分
長期優良住宅・・・・・・新築後5年度分
免税点
同一の納税義務者が町内に所有する資産の課税標準額を土地・家屋・償却資産ごとに合計したとき、次の金額に満たない場合は固定資産税が課税されません。この金額を免税点といいます。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
償却資産について
償却資産とは、会社や個人が工場や商店などを経営している場合で、これらの事業のために使用することができる有形資産のことをいいます。
土地、家屋、自動車など一部の資産を除き、事業のために使用される資産のほとんどが該当します。
【事業のために使用できる】とは・・・
「事業のために」とは、工場の製造機械など直接的に利益を生み出す資産だけでなく、駐車場のアスファルト舗装や、門・塀などの間接的に事業のために使用される資産も対象になります。
償却資産の分類
1.構築物 (広告塔、舗装路面、フェンス、門、塀など)
2.機械及び装置 (旋盤、ポンプ、太陽光発電設備など)
3.船舶
4.航空機
5.車両および運搬具 (貨車、客車、大型特殊自動車など)
6.工具、器具、備品 (パソコン、机、いす、測定工具など)
償却資産の申告
会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で1月1日現在に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における償却資産の状況を1月31日までに申告してください。
納期限
毎年、4月中旬に固定資産税納税通知書を送付します。原則、納税通知書に記載された税額を4回に分けて納税していただきます。
各納期限は、
第1期・・・4月末
第2期・・・7月末
第3期・・・9月末
第4期・・・1月末
※評価替えの行われる年度は、納税通知書が5月中旬に発送されることから、第1期の納期限も5月末となりますので、ご注意ください。また、各納期限が土・日曜日、祝祭日の場合は、翌営業日が納期限となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務住民課 課税係
〒969-1692
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7
電話:024-582-2114
ファクス:024-582-1028
メールフォームによるお問い合せ