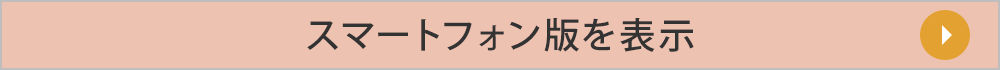9月20日ハンバーグの話
更新日:2024年09月24日
今日の献立は、ごはん、牛乳、おろしハンバーグ、ひじき炒め、もやしのみそ汁です。
ひじき炒めの人参が桑折町産です。
ハンバーグは、中央アジアの遊牧民(タルタル人)が食べていたタルタルステーキが起源といわれています。
タルタルステーキは、硬い馬肉を食べやすくするために細かく肉を叩き、これにみじん切りした玉ねぎや塩などで味付けして生で食べる料理です。
18世紀にドイツのハンブルグから伝わり、固めの牛肉などをひき肉にして、つなぎにパン粉を加え、玉ねぎや香辛料などで味つけして、円形に練り固めて焼く食べ方に変わりました。
【クイズ】
今では、お肉は毎日当たり前のように食べていますが、日本人が肉をよく食べるようになったのは何時代からでしょうか?
1.縄文時代 2.江戸時代 3.明治時代
正解は、3.の「明治時代」からです。
江戸時代までは、毎日肉を食べる習慣はありませんでした。
明治時代に文明開化として肉を食べることが進められてから肉を食べるようになりました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育文化課 学校給食センター
〒969-1661
福島県伊達郡桑折町大字上郡字堰上45番地
電話:024-581-0250
ファクス:024-581-0251